

バイオ燃料とバイクの未来技術
バイオ燃料のバイクレースでの世界初採用事例

図解入門よくわかる最新バイオ燃料の基本と仕組み (How-nual図解入門Visual Guide Book)
2023年、モータースポーツの世界に大きな革新が起こりました。全日本ロードレース選手権の最高峰クラスであるJSB1000において、世界の二輪レースに先駆けて100%カーボンニュートラル燃料の使用が義務化されたのです。この歴史的な一歩は、二輪モータースポーツにおける環境配慮への重要な転換点となりました。
使用された燃料は独ハルターマン・カーレス社の「ETS Renewablaze Nihon R100」で、植物ごみや木材チップなどのバイオマスを原料としています。化石由来の原料を一切使用していないこの特殊な燃料は、サーキットに独特の香りを漂わせました。
注目すべきは、この環境に配慮した取り組みが、レースの迫力や性能を損なわなかった点です。当初はパワーダウンが懸念されていましたが、予選でポールポジションを獲得したヤマハの選手たちは、前シーズンを上回るタイムを記録。決勝レースでも中須賀選手が2回とも優勝するなど、従来の燃料と遜色ない性能を発揮しました。
この先進的な取り組みは、MotoGPが2025年に40%非化石由来燃料、2027年に100%非化石由来燃料の採用を予定しているのに比べて、かなり早い段階での実用化となりました。日本のモータースポーツが世界に先駆けて環境技術の実証の場となったことは特筆すべき点です。
バイオ燃料バイクの種類と特徴について
バイクに使用されるバイオ燃料には、いくつかの種類があります。それぞれ原料や製造方法、特性が異なるため、用途に応じた選択が重要です。
まず、バイオエタノールはガソリンエンジン向けの代替燃料として広く知られています。農作物や木材、古紙などの植物由来の糖分を微生物によってアルコール発酵させて製造される液体アルコール(C₂H₅OH)です。世界燃料憲章では混合率によってE3(3%混合)、E10(10%混合)などと表記されます。日本では2003年の法改正で既存のガソリン車向けにE3の使用が認められ、対応車に限りE10の利用も可能となっています。
次に、バイオディーゼルは主にディーゼルエンジン向けの燃料です。菜種油、パーム油、大豆油、魚油・獣油、廃食用油などのバイオマス由来の油脂を原料としています。脂肪酸メチルエステル(FAME)と、水素処理した直鎖のdrop-in燃料である水素化植物油(HVO)の2種類があります。
また、バイオETBEはガソリンの精製過程などで副生されるイソブテンとバイオエタノールを化学合成して製造される燃料です。オクタン価向上剤としてガソリンへの添加利用が可能で、体積比で7%程度まで混合しても自動車性能には影響がありません。
さらに、バイオブタノールは次世代バイオ燃料として注目されています。エタノールと比較して熱量がガソリンに近く、吸湿性の問題も少ないという利点があります。また、ガソリンだけでなく軽油にも混合して利用できる汎用性の高さも特徴です。
これらのバイオ燃料は、従来の化石燃料と比較して、燃焼特性や取り扱い方法に違いがあるため、エンジンの調整や適切な管理が必要となります。
バイオ燃料バイクの世界記録と性能評価
バイオ燃料を使用したバイクの性能は、従来の化石燃料バイクと比較してどうなのでしょうか。実際の記録から見てみましょう。
2009年、バイオディーゼルを使用したバイクが時速210kmという驚異的な速度記録を樹立しました。このマシンはBMW R1150RTをベースに、BMW 3シリーズの2リッターディーゼルエンジンを組み込んだカスタムバイクでした。カリフォルニア州オークランドのインダストリアルアーツグループ「the Crucible」のMichael Sturtz氏とそのチームによって開発され、制作コストは約230万円、制作期間は6ヶ月を要したとのことです。
この記録は、当時の電気バイクの世界最速記録である時速約250kmには及ばないものの、バイオ燃料バイクの高いポテンシャルを示す重要な成果でした。
また、実際のレース現場での性能評価も注目に値します。全日本ロードレース選手権JSB1000クラスでカーボンニュートラル燃料を導入した際、各チームは当初、燃料の特性に合わせたセッティングに苦労しました。バイオ燃料は従来のレース燃料と比べると燃えにくく、点火系の制御を最適化する必要があったのです。
しかし、技術者たちの努力により、予選では前年のポールポジションタイムを上回るタイムを記録。決勝レースでも安定した走りを見せ、通常の燃料と遜色ない性能を発揮しました。これは、適切なエンジン調整によって、バイオ燃料でも高いパフォーマンスが得られることを実証した重要な事例です。
一方で、オイルの劣化が早まるという新たな課題も明らかになりました。燃え残った燃料がオイルに混ざり、オイルが希釈されるスピードが通常より速いという問題が報告されています。これはバイオ燃料特有の課題として、今後の技術開発で解決が期待される点です。
バイオ燃料のバイクエンジン調整技術
バイオ燃料をバイクで効率的に使用するためには、従来の化石燃料とは異なる特性に合わせたエンジン調整が必要です。この技術的なノウハウは、レース現場から一般のバイクユーザーにも徐々に広がりつつあります。
まず重要なのは、点火系統の最適化です。バイオ燃料は一般的に燃えにくい特性があるため、点火タイミングや点火エネルギーの調整が必要となります。全日本ロードレース選手権のJSB1000クラスでは、各チームがカーボンニュートラル燃料に合わせた点火マップを新たに作成し、最適な燃焼効率を追求しました。
燃料噴射システムの調整も重要です。バイオエタノールやバイオディーゼルは、従来の燃料と比較して発熱量や気化特性が異なります。そのため、噴射量や噴射タイミングの微調整が必要となります。特にエタノール混合燃料は、混合率によって必要な噴射量が変わるため、フレキシブルな制御システムが求められます。
また、冷間始動時の対応も課題の一つです。バイオエタノールは低温での始動性に課題があるため、寒冷地や冬季の使用では、始動性を確保するための特別な対策が必要となることがあります。プレヒーターの装着や、始動時の燃料噴射量増加などの対策が考えられます。
さらに、バイオ燃料使用時のエンジンオイル管理も重要なポイントです。全日本ロードレース選手権の現場では、バイオ燃料の使用によりオイルの劣化が早まることが報告されています。これは燃え残った燃料がオイルに混ざり、希釈を早めるためと考えられています。そのため、従来よりも頻繁なオイル交換や、より高品質なオイルの使用が推奨されます。
これらの調整技術は、レース現場でのデータ蓄積によって日々進化しています。国内二輪車メーカー4社も技術的、経済的支援を通じて、バイオ燃料に最適化されたエンジン制御技術の開発を進めており、将来的には一般市販車にもこの知見が活かされることが期待されています。
バイオ燃料バイクの未来と環境貢献の可能性
バイオ燃料を活用したバイクの普及は、モータースポーツの世界だけでなく、環境問題への貢献という側面からも大きな可能性を秘めています。その未来像と環境への影響について考察してみましょう。
世界的なカーボンニュートラル実現に向けた動きが加速する中、二輪車業界も大きな転換点を迎えています。MotoGPでは2024年から40%以上、2027年からは100%を非化石燃料とすることが義務付けられました。これに先駆けて日本の全日本ロードレース選手権が100%カーボンニュートラル燃料を導入したことは、世界的にも注目される先進的な取り組みです。
特に注目すべきは「第2世代」と呼ばれるバイオ燃料の開発です。初期のバイオ燃料は食用作物を原料としていたため、食料問題との競合が懸念されていました。しかし現在は、食用にならない藻類や廃棄される使用済み植物油、生ゴミ、下水汚泥、家畜糞尿などを材料とする「第2世代」バイオ燃料の開発が進んでいます。これにより、食料問題を悪化させることなく、持続可能な形での燃料供給が可能になりつつあります。
また、バイオ燃料の大きな利点として、既存のエンジンやインフラを大きく変更せずに使用できる点が挙げられます。国際自動車連盟(FIA)は、2030年までに道路上には18億台の自動車が存在し、そのうちBEV(バッテリー電気自動車)はわずか8%と推定しています。つまり、内燃機関は今後も長期にわたって重要な動力源であり続けると考えられます。バイオ燃料は、そうした既存の内燃機関を活かしながら、環境負荷を低減できる現実的な解決策となる可能性があります。
日本のバイクメーカーも積極的に取り組みを進めています。ヤマハ発動機は水素エンジンの技術開発を行い、本田技研工業、スズキ、川崎重工と共に二輪車における内燃機関を活用したカーボンニュートラル実現への可能性を探っています。また、マツダは100%バイオ由来のディーゼル燃料を使用する「MAZDA SPIRIT RACING Bio concept DEMIO」でスーパー耐久レースに参戦するなど、実証実験も進んでいます。
課題としては、バイオ燃料の生産コストの高さが挙げられます。現状では通常の燃料と比べて2倍程度の価格となっており、普及のためにはコスト低減が必要です。全日本ロードレース選手権では、二輪車メーカーやタイヤメーカーなどが費用を分担することで、1リットル当たり1500円程度の燃料を400円で提供していますが、それでも通常燃料の2倍のコストとなっています。
しかし、技術の進歩と量産効果によるコスト低減、そして環境価値の社会的認知が進めば、バイオ燃料バイクの普及は加速する可能性があります。モータースポーツの現場で蓄積された知見が一般の二輪車にも活かされ、カーボンニュートラルな移動手段としてのバイクの価値が再評価される日も、そう遠くないかもしれません。
バイオ燃料バイクは、環境に配慮しながらも、バイクの持つ走る楽しさを損なわない次世代の移動手段として、大きな可能性を秘めているのです。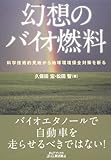
幻想のバイオ燃料 (B&Tブックス)